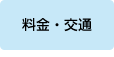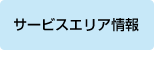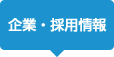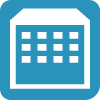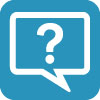- ホーム >
- お知らせ・ニュースリリース >
- 第1回 四国横断自動車道 吉野川渡河部の環境保全に関する橋梁部会(議事要旨)
お知らせ
第1回 四国横断自動車道 吉野川渡河部の環境保全に関する橋梁部会(議事要旨)
1.日時
平成25年10月29日(火曜)10時00分~12時00分
2.場所
アスティとくしま1階 第2会議室
3.出席者
- 出席委員:
- 成行部会長、長尾副部会長、真田委員、橋本委員
- オブザーバー:
-
国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 兵頭副所長
徳島県 県土整備部 道路局 小林局長 - 事業者(事務局): 西日本高速道路株式会社 四国支社 建設事業部
-
松室部長
建設課 大木課長
徳島工事事務所 大内所長
徳島工事事務所 徳島東工事区 登倉工事長
4.議題
1)開会
2)事業者挨拶
3)議事ならびに説明事項
-
事務局から資料2「
第1回橋梁部会の進め方(114KB)
 」を説明。
」を説明。
-
道路構造検討方針
-
事務局から資料2「
道路構造検討方針(147KB)
 」を説明。
」を説明。
-
先行事例である阿波しらさぎ大橋建設事業における、シギ科・チドリ科の個体数の変化に関する質問があった。
⇒事務局から、先行事例においては、工事中若しくは上部工が完成した以降も継続的に河口干潟に飛来している状況であり、年次的な個体数の変化は自然的な変動であると説明した。
-
鳥類は、主塔やケーブルが存在すると上空に避けるように飛翔することは明らかになっているのか質問があった。
⇒事務局から、第1回環境部会の中で、シギ科・チドリ科は捕食者等の外敵に対して、上空から襲われることを意識しており、回避行動としてより上空を飛翔する傾向にあるという意見があったことを報告し、橋梁形式の検討の方向性としては、桁橋を採用していきたいことを説明した。
-
先行事例である阿波しらさぎ大橋建設事業における、シギ科・チドリ科の個体数の変化に関する質問があった。
-
事務局から資料2「
道路構造検討方針(147KB)
-
橋梁計画条件の整理
-
事務局から資料2「
橋梁計画条件の整理(1,253KB)
 」を説明。
」を説明。
-
事務局から資料2「
橋梁計画条件の整理(1,253KB)
-
橋梁形式の検討(橋梁形式案の提示)
-
事務局から資料2「
橋梁形式の検討(橋梁形式案の提示)(2,912KB)
 」を説明。
」を説明。
-
橋梁計画案のコンセプトとして、「環境の価値を踏まえた地形改変場所を検討する」の項目は、基本的に着目するべき場所がないということか質問があった。
⇒事務局から、第1回環境部会の中で、希少生物が多く生息するホットスポットが存在する場合、その様な場所に橋脚を設置しない方が良いという意見があったことを報告し、渡河部周辺の環境は先行事例と事前調査の底生生物調査の結果から多様性がある空間といえるが、自然のゆらぎによる地形変動が大きく、ホットスポットと言える場所が見いだせないと考えていることを説明した。
-
橋梁構造に対する橋梁案の評価のうち、景観の閉塞性について具体的に説明して欲しいとの質問があった。
⇒事務局から、第1回検討会の中で、吉野川の東端の河口部で事業が実施されることから、吉野川の景観の開放性に関する評価が求められたことを報告し、本部会で提示した橋梁形式の桁高、橋脚数を踏まえて、3案ともに差別化できないことから中間と評価したことを説明した。
-
橋梁構造に対する橋梁案の評価のうち、維持管理性の付属物について具体的に説明して欲しいとの質問があった。
⇒事務局から、付属物は主に支承のことを示しており、橋脚数が多くなることで、点検による維持管理が増えることを説明した。
-
その他、今後、橋梁形式を検討していく上で配慮すべき項目等について各委員から以下のご意見をいただいた。
- 1)
-
景観に関すること
- 左岸の橋台位置をもう少し下げられるか検討すること。
- 橋の箱桁断面形状について、もう少しシャープに見えるよう箱桁ウェブに傾斜をつけるなど工夫すること。
- 橋梁の高欄は、半壁高欄形式を検討するとともに、その高欄のコンクリート面については経年的な汚れ防止対策を検討すること。
- 2)
-
二酸化炭素の排出量削減に関すること
二酸化炭素の排出量削減の観点から、構造物の形式を決める上であまり二酸化炭素を排出しない方法とするのが好ましい。また、浚渫に伴う施工重機から多く排出されることや、コンクリート桁橋となる場合、コンクリート材料に廃棄物を使用できることなど踏まえると環境面から、第2案が優位と考えられる。
-
橋梁計画案のコンセプトとして、「環境の価値を踏まえた地形改変場所を検討する」の項目は、基本的に着目するべき場所がないということか質問があった。
-
事務局から資料2「
橋梁形式の検討(橋梁形式案の提示)(2,912KB)
5.閉会
配付資料
- 資料2 説明資料