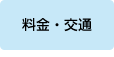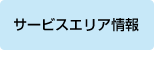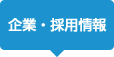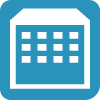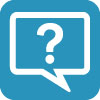- ホーム >
- お知らせ・ニュースリリース >
- 第17回 四国横断自動車道 吉野川渡河部の環境保全に関する検討会(議事概要)
お知らせ
第17回 四国横断自動車道 吉野川渡河部の環境保全に関する検討会(議事概要)
1.日時
令和6年3月13日(水) 10時00分~12時00分
2.場所
徳島県教育会館 本館5階 ホール
3.出席者
- 出席委員:
- 山中座長、中野部会長、鎌田副部会長、成行部会長、長尾副部会長、大田委員、桑江委員、橋本委員、浜野委員、和田委員
- オブザーバー:
-
国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所 水野 副所長
徳島県 県土整備部 高規格道路課 明星 副課長 - 事業者:
- 西日本高速道路株式会社 四国支社
-
建設・改築事業部 大城部長
建設・改築事業部 衛藤構造担当部長
建設・改築事業部 古賀課長代理
徳島工事事務所 長谷川所長
徳島工事事務所 中谷工務課長
4.議題
(1)開会
(2)事業者挨拶
(3)議事ならびに説明事項
- 事業者から「土木学会デザイン賞、田中賞の受賞についての報告」を報告。
-
第16回検討会の課題への対応
-
事業者から資料1に基づき、「
第16回検討会の課題への対応(128KB)
 」を説明。
」を説明。
-
事業者から資料1に基づき、「
第16回検討会の課題への対応(128KB)
-
総合評価報告書について
-
事業者から資料1に基づき、「
総合評価報告書について(614KB)
 」を説明。
」を説明。
-
事業者から資料1に基づき、「
総合評価報告書について(614KB)
-
今後のデータ公開について
-
事業者から資料1に基づき、「
今後のデータ公開について(348KB)
 」を説明。
」を説明。
-
事業者から資料1に基づき、「
今後のデータ公開について(348KB)
-
検討会の閉幕
-
事業者から資料1に基づき、「
検討会の閉幕(405KB)
 」を説明。
」を説明。
※本項目について、以下の意見を踏まえて、総合影響評価報告書及び四国横断自動車道吉野川渡河部の環境保全に関する検討会の終了について了承された。
※以下に、委員からあった主な意見等をまとめる。
-
委員から、「データ提供時の希少種の取り扱いはどうするのか、マスクをかけて提供するのか。」との質問があった。
⇒ 事業者より、「情報開示の請求を受けたとしても、会社の方針として、希少種のデータに関しては、基本的にマスクをかけた状態での提供となる。ただし、研究目的等の理由があれば、相談いただいたうえで、柔軟に対応する予定である。」との説明があった。
-
委員から、「希少種のデータが無ければ分析等が出来なくなる可能性があるため、希少種に関するデータについても提供の手続きが可能な状態にし、HP上に手続きの方法をわかりやすく示していただければと思う。」、「提供するデータは、電子データで提供するのか。」との意見と質問があった。
⇒ 事業者より、「情報公開の手続きをいただければ、エクセルデータ等のデータ形式で提供することが可能である。」との説明があった。
-
委員から、「別添資料の環境対策に要した費用について、環境調査費が建設費の1%という金額は適切であるのか、客観的な評価が必要ではないか。」、「例えば、今回の倍の費用をかけたときにどれくらいのデータが得られて、精度がどれくらい上がるのかといったこと、環境調査費が建設費の1%が適切であるかどうかを評価することが、今後の事業をより良くすることにつながると思う。」、「影響評価報告書に記載することではないかもしれないが、事業者としてそういった情報を整理することが大事である。」、「世界的な標準のレベルはどれくらいであるか、橋梁を運用していく中で、利益が何パーセントあって、その中の何パーセントで環境対策費用としたのか。すぐに計算できるようなものではないが、そういった視点が、今後、重要となる。」「吉野川河口域に橋梁が残り続けるため、事業が終了し、影響がなかったからと言って、関係を断つのではなく、吉野川河口域の環境がより良くなるような働きかけや活動に協力していただきたい。」との意見があった。
⇒ 事業者より、「環境対策に関する費用に関しての妥当性を評価するのは非常に難しく、会社として、必要な費用を計上した結果を説明させていただいた。」との説明があった。
-
委員から、「説明いただいた費用は、環境調査に対するものだけであるということか。」、「環境配慮対策による建設費のコストアップは明確ではないということでよろしいか。」「しっかりと環境配慮対策をしていただいているとは感じているおり、新技術の導入等、色々なコストアップの面があると思うが、内部的に今回の事業を評価していただいて、コストに見合うものであったのかを評価していただければ。」、「環境対策することで魅力・価値が上がったなどの情報を整理することで、今後、このような環境影響評価を続けていくことに繋がると思う。」、「今後の吉野川河口域との関わり方はどう考えているのか。」との意見があった。
⇒ 事業者より、「基本的には、今後、高速道路事務所の管理となる。今のところ河川に特化した関わりを考えてはいないが、道路周りの清掃活動に参加等、今までと変わりなく、地域と関わり続けられればと考えている。」との説明があった。
- 委員から、「鳥類の調査に関して、普段は調査しないようなデータ(鳥類の飛翔高度に関するデータ)を整理しており、学術的に非常に貴重なものである。そのため、論文等の形で取りまとめることで、非常に価値が生まれるものだと考えている。」、「今後、事業者としての関わりとして徳島大学等と連携し、論文を執筆する等の対応があるのではないか。」、「そういったことが、環境対策にかけた費用のコスト回収に繋がるのでは。」との意見があった。
-
委員から、「今回、いろいろな取り組みがあり、その中でハビタットのバックアップによる影響評価の考え方は新しいと思うが、学術的に正しいかどうかは公表されているものではなく、世に問うべきものも含まれていると思う。」、「デザイン賞をいただいたことは、細部にわたって検討し、真摯に対応することが表彰に結びついていると思う。」、「そのため、影響評価報告書を一般の方、一般の技術者に提供できるようにもう少しわかりやすく、冊子として提供できるようにしていただければと思う。」、「非常に難しいことだとは思うが、吉野川はたくさんの市民が熱意をもって様々な取り組みを行っているので、活動への助成金といった形でつながり、市民によるモニタリング等、吉野川の環境がよりよくなるように協力していただければと思う。」との意見があった。
⇒ 事業者より、「吉野川サンライズ大橋は、今後も吉野川河口域に残り続けるものであることは認識しており、この場で、何ができるのかすぐに回答できるものではないが、共存の方法について、社内で引き続き検討させていただく。」との説明があった。
-
委員から、「現時点でも報告書の修正は可能であるか。」との意見があった。
⇒ 事業者より、「可能である。」との回答があった。
-
委員から、「パブリックコメントに対する回答 資料3 P9のご意見5-2についてだが、この意見については、今後の課題として取り組みますと修正したほうが良いのでは、また、影響評価報告書の課題にも書き加えたほうが良いのでは。」、「影響評価報告書についての指摘であるが、2-81ページの下部工の影響評価に関する課題の文面について、個体湿重量が重たいと書かれているが、口語調のため、報告書の文面としてはふさわしくない。大きいと書き換えたほうが良いのではないか。」、「同じく下部工の影響評価に関する課題の文面であるが、分析が困難であると書かれており、その理由を述べているが、この文面では、分析を試みた結果、困難であったという表現となっている。ここでは、そもそもの分析が困難であったことを述べている箇所なので、事業の影響評価として、困難な条件が備わっていた文面にするほうが論理的に正しい文章となるのでは。」との意見があった。
⇒ 他の委員より、「文面の修正については問題ないと思うが、パブリックコメントの回答に対する説明をお願いする。」との意見があった。
⇒ 事業者より、「資料3 9ページのご意見5-2に関する指摘だと認識している。コアジサシ、ビロードキンクロ、クロガモといった重要種に関する質問となるが、この意見を受けてデータを再確認した。その結果、事前と工事中に出現していることが確認された。また、下部工の工事が始まった時には確認無し、上部工の桁が張り出したタイミングで多く出現しているデータといった年によりばらつきのある結果が確認された。一方で、供用開始後には出現が少ない結果となっている。これは、調査時期が4月の後半と5月の頭で調査を実施していることが関係していると考えている。個人的な感覚として吉野川を見ていると5月後半からよく出現していると認識している。また、コアジサシは夏鳥であるため、夏に近づくほど出現が増えると理解している。そのため、シギ・チドリ類の渡りに注目した関係上、5月の前半に調査を実施しており、コアジサシの出現については、追いかけられなかったと考えている。結果として工事後の調査で数が少なくなった状況であった。」、「ビロードキンクロとクロガモに関しては、鳥類調査を数多く実施しているが、データ上ではほとんど確認されておらず、その出現に関して評価することは難しい。一方で、ビロードキンクロ、クロガモは、非常に希少価値が高い種であること、この2種が飛来する吉野川河口が非常に重要な環境であることは認識している。」「以上をまとめると事業の影響評価として、シギ・チドリ類の状況については、今までの検討会でも示してきたが、個別の種に対する詳しい出現状況の評価に対してまでは検討できていない。」との説明があった。
-
委員から、「重要種のある程度の出現状況については、把握しているということでよいか。」「そうであるならば、先程も意見した通り、パブリックコメントに対して、もう少し詳しく回答いただきたい。」との意見があった。
⇒ 事業者より、「コアジサシ、ビロードキンクロ、クロガモに限らず、鳥類調査で確認された種の事前・工事中・工事後の状況を確認しているが、その中で、重要種であるコアジサシのみが、事前調査、工事中調査と比較して工事後調査で減少している状況である。そのため、ご指摘いただいたとおり、パブリックコメントに対する回答については、もう少し丁寧な説明ができるように修正させていただく。」との説明があった。
⇒ 委員から、「鳥類調査の結果からシギ・チドリ類に影響が出ていないこと、コアジサシを狙った調査ではないので、評価が困難な条件であることを整理し、パブリックコメントの回答に記載するほうが良い。」との意見があった。
- 委員から、「現場近くにヤードが確保できたといった条件もあり、上部工をプレキャストで施工したことは、生産性の向上や環境へ良い効果を与えていると思う。また、結果的にシンプルであったと書かれていたが、防災上にも環境上にも良かったのではと思う。」との意見があった。
-
委員から、「環境対策に関しての費用についての質問であるが、これを距離で割るとどれくらいの規模になるのか。また、伊予~内子五十崎と比較してどれくらいの規模になるのか。」との意見があった。
⇒ 事業者より、「伊予~内子五十崎関しては、6.3kmのため、単純に比較すると4、5倍の規模になる。」との説明があった。
-
委員から、「総工費で600億円との説明があったが、上部工と下部工でどれくらいの比率になっているのか。」との意見があった。
⇒ 事業者より、「今回の工事は、大きく分けると上部工、下部工、浚渫に分けられ、浚渫に関しては、上部工、下部工どちらの施工時にも関係している。そのため、ざっくり説明すると上部工で半分、下部工と浚渫で残り半分くらいである。」との説明があった。
-
委員から、「今回の環境調査、施工方法が今後、生かされるようにしていただきたい。」「環境に関する費用は、8億円と説明されていたが、当初の予算では、どれくらいを想定していたのか。」との意見があった。
⇒ 事業者より、「事前調査によりある程度の規模を見込んでいたため、多少の増減はあるが、おおむね予定通りである。」との説明があった。
-
委員から、「データ提供時の希少種の取り扱いはどうするのか、マスクをかけて提供するのか。」との質問があった。
-
事業者から資料1に基づき、「
検討会の閉幕(405KB)
(4)座長による検討会終了に関する挨拶
(5)事業者による検討会終了に関する挨拶
(6)閉会
配付資料
-
資料1 説明資料(560KB)

- 資料2 徳島南部自動車道 吉野川河口域に与える影響の総合評価報告書
-
01_第1章_表紙・目次・事業概要(8,956KB)

-
02_第2章_事業の影響評価に関する各種検討(23,371KB)

-
03_第3章_環境モニタリング調査_3.1調査概要(303KB)

-
04_第3章_環境モニタリング調査_3.2騒音・振動調査(3,034KB)

-
05_第3章_環境モニタリング調査_3.3水質調査(6,107KB)

-
06_第3章_環境モニタリング調査_3.4地形調査(26,241KB)

-
07_第3章_環境モニタリング調査_3.5底生生物・底質調査(9,792KB)

-
08_第3章_環境モニタリング調査_3.6鳥類調査(10,555KB)

-
09_第3章_環境モニタリング調査_3.7魚類調査(846KB)

最新のお知らせ・ニュースリリース
2026年2月25日
2026年2月25日
2026年2月25日